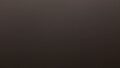東京の夜は、いつも孤独だった。ビルの隙間から漏れるネオンの光、遠くを走る車の音、そして空っぽの部屋。私は今日も一人でワイングラスを傾けていた。
スマホが震えた。画面には「翔太」の名前。
——会いたい。
短いメッセージ。それだけで、心臓が跳ね上がる。彼とは大学時代の友人だったが、特別な存在だった。卒業後、私は出版社に就職し、翔太は海外へ旅立った。そして数年ぶりの再会が、この夜を特別なものにしようとしていた。
「今、どこ?」
「すぐ迎えに行く。」
返信する前に、彼からの電話が鳴った。
「まだ起きてるよね?」
声が低くて、少し掠れている。耳元でその声を聞くだけで、肌が熱くなる。
「うん…。」
「下、来てる。」
慌てて上着を羽織り、エレベーターを降りる。マンションのエントランスの向こう、黒い車にもたれかかる彼の姿があった。
「久しぶり。」
笑顔の奥に、何か言いたそうな寂しさを感じた。
「乗って。」
彼の車に乗り込んだ瞬間、心の奥がざわつく。夜の東京が、まるで二人のための舞台のように思えた。
「どこ行くの?」
「ちょっと遠回りしよう。」
車は静かに走り出した。彼の横顔を盗み見る。相変わらず、端正な顔立ち。けれど、少しだけ大人びていた。
「元気だった?」
「まぁね。でも、ずっと…会いたかった。」
言葉が喉に詰まる。彼の視線が、信号待ちの隙に私を捉える。その瞳に、あの頃と同じ熱が宿っていることに気づいてしまった。
「ねぇ、翔太…。」
呼んだ瞬間、彼の手が私の手に重なった。温かくて、力強い。
「俺、ずっと後悔してたんだ。」
「何を…?」
「お前を、あの時…置いていったこと。」
心臓が痛いほど鳴る。言葉が出ない。車は人気のない海沿いの道に入っていた。
「忘れられなかった。」
囁くような声が、暗闇に溶けていく。
「私も…。」
それだけで十分だった。彼が車を止め、私を引き寄せる。その唇が近づいてきて、すべての理性が溶けていく。
夜風が冷たいのに、体は燃えるように熱かった。彼の腕の中で、私は過去も未来もすべて忘れた。
「もう二度と、離さない。」
その誓いが、夜明けの空に溶けていった。
——これは、終わらない恋の始まりだった。