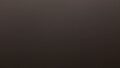都会の雑踏を抜けた先に、小さなカフェ「メモリーズ」がある。そこは、私——咲(さき)が高校時代に毎日のように通った、思い出の場所だ。
今日、久しぶりにそのカフェの扉を押し開けた。コーヒーの香りと、微かに漂うバニラの甘い香りが、あの頃の記憶を一瞬で呼び戻す。変わらない内装と、壁に飾られた色褪せたポラロイド写真の数々。どれも、10年前と同じ。
「いらっしゃいませ。」
その声を聞いた瞬間、心臓が大きく跳ねた。カウンターの奥に立つのは、紛れもなく彼——翔太(しょうた)。私の初恋の人。
目が合った瞬間、時が止まったかのようだった。翔太も驚いた表情を浮かべ、数秒の沈黙の後、少しぎこちなく微笑んだ。
「咲…?」
「久しぶり…だね。」
声が震えそうになるのを必死に堪えながら、私はカウンターの隅の席に座った。彼がここにいることに驚きながらも、心のどこかで期待していた自分がいたことを、否定できなかった。
「コーヒー、いつものブレンドでいい?」
その言葉が胸に刺さる。10年前、私がいつも頼んでいたのを覚えていてくれたことに、言葉にならない感情が溢れそうになる。
「うん、お願い。」
温かいカップを手にしながら、10年前の思い出が次々と蘇る。高校3年の冬、私は翔太に想いを伝えられないまま、卒業と同時にこの街を離れた。彼に言えなかった「好き」という気持ちが、今も心の奥底に燻っている。
「最近、どうしてた?」
翔太が静かに尋ねる。私は東京での忙しい日々について簡単に話した。でも、本当はもっと話したかった。彼が今、どんな生活をしているのか、誰と一緒にいるのか——そんなことを聞きたい自分がいた。
「ここ、まだ続けてたんだね。」
「うん。親が店を譲ってくれて、今は俺がオーナーみたいなもんかな。」
彼がこのカフェを守り続けていたことを知り、胸が温かくなる。会話は自然に流れ、昔話に花が咲いた。忘れていたはずの思い出が、鮮やかに甦る。
そして、ふとした沈黙の中、彼がぽつりと呟いた。
「…咲がいなくなって、寂しかったよ。」
その言葉が、私の心の奥を強く揺さぶった。10年分の想いが、一気に込み上げてくる。
「私も…ずっと、翔太のこと…忘れられなかった。」
言葉にした瞬間、胸が締め付けられるようだった。でも、同時に心が解放されるような気持ちにもなった。
彼がそっと手を伸ばし、私の手に触れた。その温もりが、すべてを物語っていた。
「もう、離れないで。」
彼の瞳が真剣で、私はただ頷くことしかできなかった。10年の時間を経て、私たちの想いはようやく交差した。
カフェ「メモリーズ」の時計が、静かに時を刻んでいた。それは、過去の思い出を抱きしめながら、これからの未来を共に歩んでいく合図のようだった。
——初恋は、終わりじゃなく、新しい始まりだった。