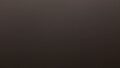その夜、彼女は一人でバーのカウンターに座っていました。
琥珀色のウイスキーグラスが手元で揺れるたび、彼女の指先は月明かりを受けて艶めいた。 白いシャツをラフに纏った男が、カウンターの隣に腰を下ろす。
「…おひとりですか?」
鋭く響く声に、彼女はグラス越しに男を見た。
「ええ、あなたも?」
「今夜はね。」
静かな夜が、二人の間をゆっくりと包み込む。バーテンダーの動きだけが時間を刻む音のように思えた。
「名前、聞いてもいい?」
「名前を聞いて、どうするの?」
「名前がわかれば、次に会った時、まただろう。」
彼女は微笑み、ほんの首を傾げた。
「…ユカ。」
「カズキだ。」
乾いたグラスがコトリと音を立てる。アルコールが二人の距離を少しずつ縮めていく。
*
夜風が二人を包み込む。
バーを出て、並んで歩く足取りは、どこかぎこちなく、それでも心地よい。
「…私たち、どこへ行くの?」
「月が綺麗だから、少し歩こう。」
川沿いの道に、白い月明かりが降り注いでいた。風がそっと二人の頬を撫でる。
「…してもキスいい?」
ユカは答えない。ただ、ゆっくりと閉じる。
彼の面倒な彼女の頬に触れ、唇が静かに重なる。
それは淡く、しかし確かな熱を伸ばしたキスだった。
「…もっと、触れてほしい。」
彼女の言葉に、カズキの腕が彼女を引き寄せる。 月明かりに照らされながら、二人の影は一つになった。
*
夜が更け、ユカはホテルの白い表紙に包まれていた。
カズキの指が彼女の髪を優しく撫でている。
「こんな夜がずっと続けばいいのに…。」
ユカが呟くと、カズキは微笑み、彼女の唇にもう一度キスを落とした。
「今は、何も考えなくて良かった。ただ、私を感じて。」
呼吸は次第に熱を帯び、二人は何度も頭を悩ませた。
その瞬間、時間はただただ、世界には二人だけが存在しているようだった。
*
朝日がカーテン越しに差し込む。
ユカは静かに目を覚まし、隣に寝息を立てるカズキを見つめた。
有線腕の中で過ごした夜は、甘く、切なく、そして永遠に思い出に残っていた瞬間だった。
「…ありがとう。」
小さく呟き、ユカはそっと彼の頬にキスをする。
それが、始まりなのか、終わりなのかはわからない。喘ぎ声を聴いてみたいと思うのは私だけだろうか?