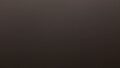夏の夜、都会の喧騒が薄れる深夜2時。麻衣(まい)は窓辺でグラスのワインを傾けながら、降り続く雨をぼんやりと眺めていた。窓ガラスを伝う雨粒が街灯の明かりを反射し、部屋の中に儚い光を散りばめている。
その日は、彼女の長年の友人であり、ひそかに想いを寄せる悠真(ゆうま)との食事会があった。二人きりではなく、共通の友人たちと賑やかに過ごしたが、彼の視線が自分にだけ少し長く止まる瞬間があったように感じていた。その微かな希望が心の奥底でじわじわと広がり、胸の鼓動を速める。
そんな中、突然スマートフォンが鳴った。画面には悠真の名前が表示されている。
「こんな時間にどうしたの?」麻衣は少し戸惑いながら電話に出る。
「ごめん、急に電話して。でも、どうしても声が聞きたくて。」
低くて落ち着いた彼の声が耳元に届くと、心臓が跳ねた。
「声が聞きたいって…何かあったの?」
「いや、ただ今日の食事会で、なんか君がずっと気になっててさ。」
「え?」
麻衣の頬が熱を帯びる。彼がこんなことを言うなんて、予想もしていなかった。
「麻衣、今から少し会えないか?」
突然の提案に驚きつつも、彼の真剣な声に抗うことができなかった。「いいよ。どこで会う?」
「君の部屋に行ってもいい?」
—
数十分後、玄関のチャイムが鳴る。麻衣がドアを開けると、雨に濡れた悠真が立っていた。黒いシャツが彼の身体に張り付き、雨粒が額から滴り落ちる。何か言おうとしたが、言葉が出てこない。
「入っていいか?」
「もちろん。」
悠真が部屋に入ると、麻衣はタオルを手渡した。彼は黙ってそれを受け取り、髪を拭きながら彼女を見つめる。その視線に引き込まれそうになる。
「どうして来たの?」麻衣が聞くと、彼は一歩近づいてきた。
「君に伝えたいことがあったから。」
彼の声は低く、少し震えていた。手を伸ばすと、麻衣の頬に触れる。温かい彼の手に、全身が包まれるような気がした。
「麻衣、ずっと君のことが好きだった。」
その言葉に息が止まる。心臓が大きな音を立てる中、彼の顔が近づいてきた。そして次の瞬間、唇が触れ合う。雨音が遠のき、世界が二人だけになったようだった。
唇を離した悠真が、「嫌だった?」と尋ねる。
「嫌なわけないじゃない。」麻衣はそう言って、彼にしがみついた。
再び彼が唇を重ねてくる。優しく、それでいて情熱的なその動きに、麻衣はすべてを委ねた。
—
雨が止む頃、二人は静かに寄り添いながらソファに座っていた。悠真の手が麻衣の髪をそっと撫でる。
「こんなに近くにいたのに、なんで今まで気持ちを言えなかったんだろう。」悠真がつぶやく。
「それは、私も同じ。」麻衣は微笑みながら答える。
その夜、二人の距離は永遠に縮まったようだった。雨が二人を繋げた運命のように、これからも一緒に歩んでいく未来が見える気がした。将来は熱い抱擁で喘ぎ声をあげながら気持ちよくなりたいとお互いに思ってる。