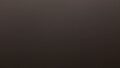冷たい風が頬を撫でる、冬の夜。街はクリスマスのイルミネーションに彩られ、人々の笑い声が響き渡っている。そんな中、千夏は一人、静かな公園のベンチに座っていた。
彼女の手元には小さな封筒。それは一週間前、郵便受けに突然届いたものだ。差出人の名前は書かれておらず、中には「12月24日、午後8時に公園で待っています」という短いメッセージだけ。最初は怪しいと思ったが、心のどこかで気になり、結局ここに来てしまった。
「やっぱり、誰も来ないか…」
時計の針は8時10分を指している。冷たい空気が肌に染みる中、彼女は小さく息を吐いた。その瞬間、足音が聞こえた。
振り向くと、そこには懐かしい顔があった。
「…悠人?」
驚きと戸惑いの混じる声が漏れる。悠人は高校時代の同級生であり、千夏の初恋の相手だった。だが、彼は10年前に突然街を離れ、それ以来音信不通だった。
「久しぶりだね、千夏。」
悠人は穏やかな笑顔を浮かべながらベンチに近づく。彼は変わらず優しげな目をしていたが、大人の落ち着きを纏っている。
「なんでここに?それに、この手紙…あなたが書いたの?」
千夏は混乱しながら封筒を差し出した。悠人はそれを一瞥し、小さくうなずく。
「うん、俺が書いた。でも驚かせたならごめん。ただ…どうしても君に会いたかった。」
悠人の声は低く、どこか切なさを含んでいた。その言葉に千夏の胸がざわつく。
「どうして急に?10年間、何の音沙汰もなかったのに。」
彼女の問いに、悠人は少し俯きながら答えた。
「いろいろあったんだ。家の事情で急に引っ越さなくちゃいけなくて、それどころじゃなかった。それからは…時間だけが過ぎてしまった。」
千夏はじっと彼の顔を見つめた。懐かしさと共に、10年前の別れ際の光景が蘇る。当時の自分は彼に何も言えず、ただ見送るしかなかった。
「でも…どうして今なの?」
悠人はポケットから小さな箱を取り出した。そして、そっと蓋を開けると、中には星形のペンダントが輝いていた。
「覚えてるかな。高校最後の文化祭の夜、君が『星を見に行きたい』って言ってたこと。あのとき、俺は何もできなかったけど、ずっと後悔してたんだ。このペンダントは、そのときの気持ちを形にしたものなんだ。」
千夏は驚きで言葉を失った。あの夜のことを、悠人が覚えてくれていたなんて。
「それに…君に伝えたかったことがある。」
悠人は深呼吸をし、真剣な目で千夏を見つめた。
「俺は君が好きだった。ずっと。」
その言葉は、冬の冷たい空気を温かく変えるようだった。千夏の心に、昔の感情が鮮やかによみがえる。
「私も…悠人のことが好きだった。」
千夏の頬がほんのり赤く染まる。悠人は安堵の笑みを浮かべ、そっとペンダントを彼女の首にかけた。
「これからは、ずっと一緒にいられる。」
そう言って、悠人は優しく千夏の手を握った。二人の間に流れる時間は、まるで10年間の空白を埋めるかのように穏やかだった。
夜空を見上げると、一筋の流れ星が輝いていた。それはまるで、二人の新しい始まりを祝福しているかのようだった。