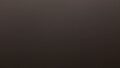小さな街の当たり前、古いレンガ造りのカフェで、杏奈はいつものようにカフェオレを注文していた。外は春風が心地よく、店内にはコーヒー豆の香りとささやかな音楽が流れている。
「また同じ席?」
店主の陽太が笑顔で質問しました。 杏奈はうなずきながら、窓際の席に腰を下ろす。 その席は、柔らかい光が差し込んでいるお気に入りの場所だった。
彼女はここ絵を描くのが日課だった。 見たもの、感じたこと、そして少しの夢を色彩で表現するのが、彼女の小さな幸せだった。
ある日、杏奈がいつものようにスケッチブックを開いていて、知らない男性が隣の席に座った。 彼は無造作に髪をかき上げながら、カフェオレを注文した。机の上に置かれたノートは、びっしりと文字が置いてありました。
「作家さんですか?」
思わず声をかけた杏奈に、男性は少し見えたように顔を上げた。
「いえ、ただの日記ですよ。でも、ちょっと書きすぎてますかね。」
それを聞いて、杏奈は微笑んだ。
その日から、彼らはカフェで顔を合わせるたびに言葉を交わしたようになった。 名前は拓海。 彼は街に引っ越してきたばかりで、このカフェが偶然の癒しの場所になったという。スケッチを、拓海は自分の日記を話題にして、終末の世界を少しずつ見るようになった。
拓海はポケットから小さな封筒を取り出した。
「これ、見てほしいんです。」
杏奈が封筒全体と、中には手書きの原稿が入っていた。
「これを出版するか迷って。でも、どうしても誰かに先に読んでほしくて。」
その物語には、日常の中に潜むささやかな優しさや希望が描かれていて、杏奈の心にじんわりと響いていた。
「拓海さんの言葉には、誰かを救う力があります。出版すべきだと思います。」
拓海はほっとしたような、でもどこか照れくさそうな表情を見せた。
その日から、杏奈のスケッチブックと拓く海の物語はみんなリンクしていくようになった。 二人は新しい物語を一緒に楽しみ、恐怖それは一冊の本となり、カフェの本棚に飾られることになった。
風とカフェオレの香りが漂う中で、二人の出会いと創作は、これからも続いていきます。