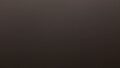都会の冬は冷たい。イルミネーションが華やぐ街並みを横目に、私は慌てて帰路をずっとでていた。その瞬間までオフィスで残業をしていたせいで、終電まで時間がない。を覚悟しながら歩くその足が、何気なく思った。
「あれ……?」
薄暗い公園のベンチに、一人の男性が座っている。 スーツ姿の彼は何も持たず、ただ一点を見つめていた。 その姿がどこか壊れやすい陶器のようなもので、気になって仕方ないがなかった。
「大丈夫ですか?」
思わず声をかけた。自分でも驚くほど無防備な行動だった。
彼が顔を上げた瞬間、胸がきゅっと締め付けられた。整った顔立ちに疲労の影が印象的なその表情は、どこか悲しげで、しかし不思議な魅力を放っていた。
「……すみません、迷惑はかかりませんか?」
ただ、どこか諦めたような響きが気になった。
「こんな寒い夜に、ここで何をしてるんですか?」
「終わりにしようかと思って……」
その言葉を聞いた瞬間、胸の鼓動が早くなる。
「終わりって……そんなのダメです!」
反射的に叫んでいた。どんな事情があるのかはわからない。
彼は私の剣幕に少し面白かったんだけど、戦闘小さく笑った。
「君、不思議な人だね。こんな知らない男に構ってくれるなんて。」
「だって、こんなところで一人でいるなんて変です。最も、温かい場所で考えた方がいいこともあります。」
それがきっかけだった。それでも、彼と駅前のカフェで熱いコーヒーを飲みながら話していた。
電話番号は翔。いる会社が暇だった、将来の暇が暇な中で、どん底の気持ちになっていたのだという。
「自分には何もないんです。ただ、流されるままに生きてきた結果がこれです。」
そんな彼に、私は自分の話をしました。 私も、仕事に追われる日々の中で何か大切なものを見ているようになってしまいました。
「人生なんて、思わないことだけ。でも……こうして話していると、不思議と希望が湧いてきますね。」
その言葉に翔は目を覚まして、穏やかに微笑んだ。
「君がいなくても、きっと今夜の僕はここにいなかったかも知れません。本当にありがとう。」
その瞬間、心の中に小さな灯火が灯るを感じた。
その後、私たちは彼と連絡を取り合い、何度も会うようになった。 翔は再び新しい仕事を探し始め、少しずつ自信を持ってた。に気づき始めていました。
やがて、イルミネーションが輝く街角で、翔が唐突に口を開いた。
「ねえ、君が僕の人生を変えてくれたんだ。」
そこで瞳がまっすぐ私を見つめている。
「君がいると、暗い夜でも明るいんだよ。だから……これからも隣にいてくれる?」
心臓が破れそうだった。
「……はい、喜んで。」
その瞬間、街の雑踏も冷たい風も消え去ったような気がした。
いよいよ、寒い冬の奇跡は私たちを越え、翔と私は新たな一歩を踏み出すことになった。 夜の公園で始まったこの物語は、これからも暖かい未来を描き続けよう。