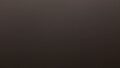薄明の街で、光子は一人、足早に通りを歩いていた。 繁忙期の仕事に追われる日々、恋愛なんて考える余裕もなかった。だけど、彼女の心の中には深い孤独が潜んでいた。
駅近くのカフェで目につきたのは、いつも同じ席に座る一人の男性だった。紺のスーツにメガネ、その手元にはいつも古びたノート。光子は彼を「ノートの彼」と心の中で誘っていました。
ある日、彼女は仕事帰りにそのカフェに立ち寄る。 彼がノートを瞬間を目撃し、ついに話しかけた。 「表情を見せたが、柔らかな笑みを落とした。「大したことじゃないですよ。…ただ、日常の断片を記録しているだけです。」
それがきっかけで、二人は少しずつ距離を縮めていった。志村は作家想いで、日常の風景や感情を書き溜めているのだと言う。忙しい仕事の中で忘れていた自分の夢を思い出した。もうすぐ頃から好きだった絵をもう一度描いてみたい、という願いだった。
二人はやがてお互いの中で、欠けていた何かを見出すようになった。 光子は志村の影響で絵を描き始め、志村は光子の言葉に励まされ、小説を仕上げる決意をした。
「僕が描く物語の中で、君がいる。君が色をくれる。」その言葉に胸が痛かった光子は、ただ静かに彼の手を握ってくれました。
夜明けが少しカフェで、二人は寄り添いながら夢を語り合った。新しい朝日が差し込むその時、彼らの物語が本当に動き出したのだ。