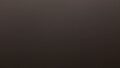冬の澄んだ夜空は、星がこんなにも輝いていたのかと驚くほど美しかった。その夜、夏目颯太(なつめ そうた)は大学の帰り道、ふと立ち寄った公園で彼女に出会った。
「見て、流れ星だよ」
声のする方を振り向くと、一人の女性がベンチに座り、夜空を指さしていた。彼女は少し上を向き、目を輝かせている。薄手のコートにマフラーを巻き、肩までの髪が風に揺れていた。
「綺麗ですね」
颯太はつられるように彼女の隣に座った。
「星を見るのが好きなんですか?」と聞くと、彼女は少しだけ微笑んで、頷いた。
「ええ。小さい頃から夜空を眺めるのが好きで…流れ星を見ると願い事をしたくなるんです」
颯太は自分のスマートフォンの画面ばかり見ていた日常を思い返し、少し恥ずかしくなった。彼女の名前は桜井結(さくらい ゆい)。颯太と同じ大学で文学部に通っているという。同じキャンパスにいたはずなのに、今日まで出会わなかった不思議を感じた。
その日から、二人は自然と話すようになった。図書館で出会えば笑顔を交わし、帰り道が同じ方向なら夜空の話をした。彼女は夢を語ることが好きで、颯太はその声を聞くのが好きだった。
「星をテーマにした小説を書きたいんです」と結が話した時、颯太はふと思った。彼女の夢を叶えるために、自分にできることはないだろうかと。
春が近づく頃、二人は一緒に郊外のプラネタリウムへ行くことになった。広いドーム型の天井に、無数の星が投影される。結は夢中になって星座の説明を聞き、颯太は彼女の横顔をじっと見つめていた。
プラネタリウムの帰り道、結が小さく言った。
「颯太君って、星みたい」
「え?」と驚く颯太に、彼女は照れたように続けた。
「颯太君と話していると、なんだか道が照らされる気がするんです。星が迷子にならないように導いてくれるみたいに」
その瞬間、颯太は自分の胸の中に小さな炎が灯るのを感じた。それは、結への特別な気持ちだった。
――でも、彼女にはすでに夢がある。その夢を壊してしまうようなことを、自分が言っていいのだろうか。
颯太は何度も心の中で葛藤した。結と過ごす時間が増えるほど、気持ちは大きくなる一方だった。
桜が咲き始めた夜、颯太はついに決意した。いつもの公園で結を呼び出し、夜空を見上げながら言葉を紡いだ。
「結さん、僕は君が星を見る理由がわかった気がする。君自身が誰かにとっての星なんだって」
「え…?」
「僕にとって、君がそうなんだ。君がいると、僕の世界が輝く。だから…これからも一緒に星を見ていたい」
結はしばらく黙っていたが、やがて顔を上げた。彼女の目には涙が浮かんでいた。
「ありがとう、颯太君。私も…君の言葉が、いつも星のように心を照らしてくれる」
その夜、二人は初めて流れ星を同じ願いで見つめた。「これからも一緒にいられますように」と。
星降る夜に、彼らの物語は新たな章を迎えたのだった。