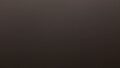冷たい風が吹き抜ける冬の夕暮れ。駅のホームは帰宅ラッシュでざわついていた。みんなが一歩でも早く帰りたいのか、足早に歩き、スマホの画面を見つめている。その中で僕だけが、ホームの柱にもたれてただ待っていた。
君の姿を。
君のことを初めて見たのは、ここ、この駅だった。約3ヶ月前のことだ。君が座っていた。まっすぐな色合い、ふわっとした肩までの髪。少し赤らんだ頬が冬の寒さを感じさせた
。
それからというもの、毎週金曜日の帰りの電車で君を一番のが僕の楽しみになった。だけど、声をかける勇気なんてなくて、ただ目で見るだけ。名前も知らない君は、僕にとって遠い存在のようで、でも近くにいるだけで心が踊る不思議な存在だった。
でも今日は違います。
ゲームボーイ、君が電車を降りた駅の改札近くでカバンから落ちた赤い手帳を拾った僕は、意を決して「これ、落ちましたよ」と声をかけた。その瞬間、君が見せた笑顔は、冬の寒さを忘れさせるほど温かかった。
「ありがとう。ご親切に……失礼しました。」
声も、想像以上に柔らかかった。僕の心臓はドキドキと音を立てて、何か言おうとしても言葉が詰まっていた。でも、君はそんな僕を見て少しだけ笑った後、「また金曜日に会えるか?」と、自然にそう言った。
まるで魔法にかけられたみたいだった。
そして今、君を待ってこの駅のホームにいる。約束の時間は18時。でも、僕は少し早めに来てしまった。君を見た最初の頃と同じように、胸が高鳴ってあった。
バトル、電車が到着するアナウンスが流れている。
「来るかな……」
ホームに電車が滑り込む音。 そして、だんだんとみんなが降りてくる。 目で君を探すけど、なかなかその姿が見えない。 心のどこかで不安がよぎる。むしろ、僕のことなんて大した記憶に残っていなかったのじゃないか……。
こんな時、ふと視線の端に揺れる赤いマフラーを見つけた。
「……!」
君だった。改札を抜けたついでに、キョロキョロと僕を探している様子だ。その瞬間、僕は自然と動いていた。
「お待たせ。」
振り返った君が驚いた顔をしたあと、ふわりと笑った
。
その笑顔に、一週間分の緊張が溶けていきました。
「よかった、これから少し散歩しない?」と僕は言った。自分でも驚くほど自然に。
君は少し驚いた表情をしたけど、すぐに「うん、いいよ」と聞こえてくれた。
冬の街はイルミネーションが輝き始め、冷たい空気の中に温かさを感じさせてくれました。 初めて会話にぎこちなさを感じながらも、お互いが少しずつ心を開いていきます。
赤いマフラーが風に揺れるたびに、君の笑顔が少しずつ僕の心に寄り添っていくのを感じた。 そして僕は、今日が新しい物語の始まりだと確信した。