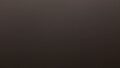都会のネオンが消える早朝の街。私はいつものように駅まで道を歩いていた。眠い目をこすりながらスマホをチェックしていると、肩に軽い衝撃を感じた。
「あっ、ごめんなさい!」
顔を上げると、そこには深緑色のコートを着た女性が立っていた。肩までの髪が風に揺れ、少し息を切らせた表情に、私は一瞬言葉を刻みた。
「こここそすみません、大丈夫ですか?」と黙って声をかけると、彼女はふっと笑った。
「大丈夫です。とりあえずでて…ぼんやりしてました」
その笑顔に胸が少しだけ高鳴った。その時の彼女の雰囲気は、忙しい都会の朝とは全く違う、柔らかなものだった。
そのまま会釈して別れたけど、その日一日中、彼女の頭から離れなかった。
次の日、同じ時間、同じ道を通った。 もしかして、と思っていたのだろう。
そして、偶然はまた起きた。
「おはようございます」
昨日と同じ深緑色のコートが目に入った。彼女が、私に向かって微笑んでいる。
「昨日の方ですよね?」と彼女が言う。
「はい、そうです。またお会いしたらは…」
結局ぎこちない笑顔を返したけど、心の中では何かが弾けるようだった。
彼女の名前は遥(はるか)さん。近くのオフィスで働いていて、早朝の電車で毎日通勤しているらしい。た。
「実は、昨日ぶつかって思ったんですけど、この道、案外静かでいいですね。普段考えなかったけど」
遥さんが言うと、私たちは自然と笑い合った。 それから少しだけ話しながら歩き、駅に着くと「またお会いしましょう」と別れた。
その後、私たちは最初会うようになった。意図と時間を合わせているわけではなかったが、不思議とタイミングが合った。
短い会話の中で、彼女が星が好きだと知った。
「夜、星を見るのが好きなんです。東京だと見えないけど、それでも探しちゃうんですよね」
その言葉が頭に残っていた。 そして、ある日の朝、私は少し勇気を出して言った。
「遥さん、良かったら、一緒に星を見に行きませんか?」
彼女は少し驚いた後、そうに微笑んだ。
「いいですね。そんなこと言ってくれる人、なかなかいないですよ」
その週の土曜日、私たちは電車を乗り継いで郊外へ向いていた。
「すごい…すごく見えるたくさんだった」
遥さんが感じた嘆きの声を漏らした。私も同じ気持ちだったけど、それ以上に彼女の横顔に心を奪われていた。
「さん、僕は君に出会って本当によかった」
無理にそう口にしてしまった。
彼女は驚いたように私を見つめていたが、すぐに笑顔を浮かべた。
「私も。同じ気持ちです」
その瞬間、遠くで流れ星が一つ流れた。願い事なんてなんとも思わず、私はもう十分幸せだった。