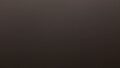駅のホームに、初夏の風が吹く。 都会の喧騒が遠くに感じられるほど、この小さな駅は静かだった。 私は電車を待ちながら、手に持った文庫本をぼんやりと眺めていた。
そのとき、ふと目に留まる人影があった。夕日が差し込む中、彼は反対側のホームに立っていた。ベージュのシャツを着たその人は、どこか懐かしさを感じさせる雰囲気を持っていた。
心臓が少しだけ早く動いた。 それは、自分でも理由がわからないくらい唐突な感覚だった。
電車が到着し、私は本を閉じて乗り込む。 ドアが閉まる直前、彼の視線がこちらを向いた気がした。 もしかしたらもしかしたら気のせいだったかもしれない。 でも、その一瞬で私の心はふわりと浮き上がった。
それから数日、私はその駅を通るたびに彼を探していた。 仕事帰りに立ち寄るこの小さな駅は、何もない景色なのに、あの日から特別な場所に思えた。受け取りませんでした。
「偶然の出会いなんて、きっとそんなものだよね」自分に言い聞かせる
ように、私はため息をついた。
ある金曜日、いつもの駅で、また文庫本を片手に電車を待っていた。そのとき、不意に声が聞こえた
。
顔を上げると、そこにはあの日見た彼がいた。 驚くほどの言葉を私に、彼は少し照れたように笑った
。この本を読んでいる姿が、なんだか印象的で…」
私の顔が熱くなるのを感じた。 まさか、彼が私を覚えていてくれたなんて
。
なった。
年齢は私とほぼ同じで、近くのカフェでバリスタをしているらしい。 立ち話の中でわかったのは、彼もこの小さな駅をよく使う私たちの生活圏は意外にも広がっていたのだ。
「これから時間、大丈夫ですか?」
突然の質問に、私は少し戸惑ったが、聞いていた。 すると彼は、「近くにおすすめのカフェがあります」と言って案内してくれた。
駅から数分歩いた場所にあるそのカフェは、温もりが感じられるアットホームな雰囲気だった。 席に着くと、大樹さんが自信たっぷりに語った
。 「そうですか。特にこのラテが評判良いですよ」
ちょっとおすすめのカフェラテを飲むと、ほんのり甘くて優しい味があった。
それから何度も彼と会えた。 駅で偶然出会った日から、私たちは少しずつ距離を縮めていった。
「ある日の夕方、大樹さんが真剣な顔で私に話しかけた。」
「本当はね、最初に君を見たときから、ずっと気になったんだ」 「どうですか
?」
駅で君を見た瞬間、なんだか心が動いたんだよね」
その言葉に、私は涙がこぼれそうになった。私も同じだったから。
夕日が差し込むカフェの窓から忘れ、二人で見た景色が見えない。この出会いが、私にとって特別なものになると、確信した瞬間だった。