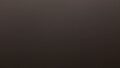六月の午後、雨上がりの空に淡い虹がかかっていた。 私は図書館の帰り道、傘を閉じて空を歩きながら歩いていた。 濡れたアスファルトの匂いと、さわやかな風が心地よい。
「すみません!」
声に向かって目を向けると、青いTシャツを着た男の子が走り寄ってきた。か見覚えのある顔だったと思った瞬間、私たちの目が合った。
「佐藤さん?」
彼は驚いた顔をして名前を聞いた。思い出した。 彼は高校時代の同級生、三浦翔。 小学校で有名なサッカー部のエースだった
。
私も微笑んで答えました。 翔は歩きながら、少し照れくさそうに笑った。 その笑顔は昔と変わらない。
「こんなところで会うなんて偶然だね。最近どうしてるの?」
彼は私の近況を聞いてきた。大学に通っていること、アルバイトで忙しいことを話すと、彼も地元のスポーツクラブで子どもたちにサッカーを教えていると言っていた。話しているうちに、自然とお互いの距離が近づいていくのがわかった。
「ちょっとお茶でも飲んで行かない?」
突然の提案に驚きつつも、私は聞いていた。近くのカフェだと、私たちは窓際の席に座った。窓の外には、まだ虹がかすかに残っている。
「佐藤さんって、昔から真面目だったよね。授業中もいつもノートをとってって」
翔は懐かしそうに言った
。 、本当だよ。俺なんか時間のけでサッカーのことだけ考えてたし」
会話は自然と高校時代の思い出に選択肢、割りの知らなかった一面を語り合った。 翔が実は数学が苦手で、私が放課後に図書室で小説を書くのが趣味だった事など、お互いの新しい一面が徐々に明らかになっていきます。
「高校の時、君に話しかけようと思ったことが何度もあったんだよね」突然
の言葉に、心臓が跳ねた。
「世界がおかしい気がしてさ」
「そんなことないよ」 私は迷って答えた。
その後の会話は妙にぎこちがなく、二人の間に静かな時間が流れた。眠っていた何かを呼び覚ましたのだ。
「また会おうよ、佐藤さん」
カフェを出るとき、翔はそう言っ
た
。
その日から、私たちは何度も会うようになった。 一緒に映画を観たり、サッカーの練習を見に行ったり。 翔の明るいさと情熱に触れるたびに、私は彼のことがもっと知りたかったそして、そんな私を彼も大切に思ってくれているのを感じた。
「俺さ、昔からずっと好きだったんだ、君のこと」その言葉
に、私は足を止めた。「本当だよ。君の笑顔を見るたびに、もっとそばにいたって思ってた。でも、言えなくて。だから、今こうして言えるのが嬉しい
」
胸がいっぱいになった。私の頬を涙が伝わったのを見て、翔が優しく
微笑んだ
。
手を加えた。
青空が広がるその瞬間、私たちの物語が本当の意味で始まったのです。