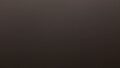春の夜空に舞う桜の花びらが、都会の喧騒を忘れさせてくれる。 広い公園のベンチに座りながら、詩織は一人ぼんやりと星空を楽しんでいた。心が疲れ切っているのを感じていた。 何か新しいことが欲しい――そう思いながら、今日も日常の延長線上にいる自分を変えられなかった。
あんなとき、ふいに近くから声がした。
驚いて振り向いてみると、そこには少し乱れたスーツを着た男性が立っていた。
「ええ……静かな時間が好きで。」 詩織は控えめに答えた。
「こんな夜に話しかけてすみません。僕も仕事帰りにここに来るのが癖になってしまいます。星を眺めて、なんだか少しだけ気持ちが軽くなるんです。」
その言葉に、詩織は少し驚いた。自分と似た気持ちを不思議な人がいて、不思議な親近感を思い出した。
「わかります。星って、不思議と心を癒してくれますよね。」
その夜、二人は初対面ではなく、自然に言葉を交わした。名前も仕事もお互いに話さないまま、ただ星や季節の話だけをして別れた。かな高い音が残った。
次の夜、詩織は再び公園に足を運んだ。 理由は自分でもわかっていた。 昨夜彼にもう一度会っていたのだ。 ベンチの近くに行くと、彼はすでにそこに座っていた。
「また来てくれたんですね。」彼が気づいて笑いを浮かべる。
「星がきれいなので、つい。」詩織も笑い返した。
それから数日間、二人は毎晩同じ時間に公園で会い、話すようになった。 詩織は気づいていた。 この時間、自分にとって特別なものになりつつあることを。て少しずつ心惹かれていることも。
「ある夜、彼が言った。
「僕、少しだけ人生が楽になりました。あなたのおかげです。」
「そんなこと、ない
ですよ。ただ話してるだけで。」
「それが大事なんです。誰かとこうして心を分け合える時間、どれだけの力になるか……知らなかった。」
詩織の胸に温かいものがあった。 こんな風に自分が誰かの力になれることが、純粋に良かった。
「私も……あなたと話すのが楽しみです。」
その一言が、二人の距離をさらに縮めました。
しかし、明日は幸せな日々は突然の終わりを迎えます。 彼がその夜、少し寂しげな表情で告げました。
「僕、からしばらくここには来られません。仕事の都合で地方に行くことになりましたた。」
詩織の心が一瞬残ったような感覚に襲われた。
「でも、また星空の下で会えたら、そのときは名前を教えてくれませんか?」
その言葉に、詩織は微笑みながら伺いました。
彼が去った後、詩織の日常は再び静かなものになった。 でも、夜空を見上げるたびに彼の言葉を思い出し、また会える日を信じていた。
以前の春の夜、詩織がいつもの公園に行って、そこには彼が立っていた。
「ただいま。」
その一言に、詩織の瞳は涙で滲んだ。
「おかえりなさい。」
そして、彼女は初めて自分の名前を伝えました。
「詩織です。」
「僕は航一。会えてよかった。」
二人はまた星空を歩きながら、これから始まる未来を静かに感じていた。