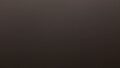春の風が心地よい夜、灯がまばらな小さな駅のホームに、一人の女性が立っていた。 彼女の名前は結衣。 30歳を過ぎ、仕事一筋で走り続けてきた彼女は、気づけば心が疲れた日常に潜む孤独感に耐え、たまたま見つけた電車に乗り、降り立ったのがこの無人駅だった。
ホームに響く静寂の中、遠くから足聞こえてきた。振り向く、スーツ姿の男性が一人、こちらに向かって歩いて来る。結衣と同じように、何かを思い出した表情をしている。
「こんな時間に、珍しいですね。」
突然かけられた結衣は驚き、少し震えた
。 」
その言葉に、結衣は全然心がなくなるのを感じ
た
。 「も、逃げてきたんです。」
その夜、二人は小さな駅のベンチで終わりの話した。 名前は交換しなかった。 ただ、仕事のストレスやふとした悩み、過去の恋愛の傷跡をぽつぽつと話し合った。安心感があった。
「こんな夜に、知らない人と話すなんて変ですよね。」
結衣が笑って、彼に持たれて笑った
。
「明日
会った何かの縁。良かったら今夜、また会わないか?」
結衣は少し考えたが、結局考えていた。
次の日の夜、結衣は前日と同じ駅に向かった。 不安と期待が交錯する中、彼はベンチに座っていた。
「来てくれて、ありがとうございます。」 彼の笑顔は心から安らぐもので、結衣の胸が少し高く鳴った。
その日も、二人はただ話した。 趣味のこと、好きな映画、行きたい場所――いくつかの細やかな会話の中で、結衣は少しずつ自分を進めようだった。
「結衣さん。」 彼がふと名前を呼んだ。
「名前、言ってなかったのに……。」
「昨日の話から予想しました。もしかして間違ってたらごめんなさい。」
「それで
、あなたの名前は?」
「涼介です。」
その後も何度か駅で会ううちに、二人はどんどん惹かれ合っていった。 ある日、涼介が結衣だった
。ます。」
結衣は静かに聞いていた。
ある日、涼介から突然のメッセージが来た。
「明日で、僕はここを離れます。でも最後にどうしても会いたい。」
「突然でごめんなさい。仕事の
都合で遠くに行くことになりました。でも… …。」
涼介は一瞬言葉を飲み込んだ後、続けた
。
代わりの言葉に、結衣は胸が締め付けられるような思いだった。
涼介が去った後、結衣はまた日常に戻った。 しかし、心のどこかで涼介の言葉を信じていた。 そしてしばらく後、駅のベンチに座る結衣の前に、涼介が現れた。
「また来ました。」その言葉に、結衣の瞳は涙
で滲んだ。
二人は静かに見つめ合いながら、また始まる物語を感じていた。