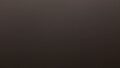夕暮れの街は、どこか切らず、どこかいて心をざわめかせた雰囲気を漂わせていた。 私はお気に入りのカフェで、いつものようにノートパソコンを開き、ぼんやりと仕事を片付けていた。不思議な気配が漂っていた。
ガラス越しに見える通りを、忙しくなく行き交う人々。 その中に、妙に目が見える人物がいた。 黒いコートに身を包み、少し無造作に整えられた髪。 肩にはカメラバッグが掛けられ、ここを見ながら微笑む彼の目、ほとんどこの瞬間を切り取っているかのように鋭く光っていた。
突然、店の扉が開いた。
「この隣、いいですか?」
と振り返って、そこには視線通りで目が合った彼が立っていた。
「え、あ、もちろんです」のんびり
してて、彼は軽く笑いながら私の隣に座った。 そして、カメラバッグから愛用のカメラを取り出し、さりげなく私の方に向けた。
「いい表情してますね。この光の中で見ると特に。」
突然の言葉に戸惑いながらも、彼の声には不思議な温かさがあった。 初対面の人にこんな風に褒められるのは慣れていない。
「写真家さんですか?」
「うん、まあそんなところ。だけど、僕はただ“瞬間”を察するのが好きなだけさ。今も、君のその表情はとてもいい。」
私の心臓が少し早くなった。なんだろう、この感覚は。彼の目は真剣で、それでいて柔らかい。まるで彼の言葉に引き寄せられるように、自然と笑みがこぼれた。
それから私たちは、コーヒーが冷めるまで話し続けた。 写真の話、旅の話、そして皆の夢の話。 まるで昔から知っていたみたいに、話題が終わることはなかった。不思議なリズムがあって、その場の空気を彩る力があった。
「ねぇ、君は何を夢見てるの?」急
に思えて、私は少し戸惑った。
言ってると思ってる。でも、それは何かはまだわからなくて。」
「そういうの、いいと思うよ。」
彼はカメラを構え、私に向けてシャッターを切った
。
その言葉が、私の中に深く食い込んだ。 彼は、私の迷いや不安さえも肯定してくれる。 いわば、この世界の中でただ一人、私を本当に理解してくれる人のように感じるた。
「今度、この街の夜景を
撮って行こうと思ってるんだけど。一緒にどう?」
勝手にお誘いに、私は迷わずうなずいた。
それから私たちは、何度も一緒に街を歩き、写真を撮り、笑い合った。 彼が切り取った写真の中には、私自身の知らない「私」が映っていた。が私の心を埋め尽くしていました。
そして、ある日の夜景撮影の帰り道。 月明かりの下で、彼はカメラを置き、真剣な顔で私を見つめていた。
「君を初めて見たときから、何か運命的なものを感じた。でも、今日確信したんだ。君と一緒にいると、どんな瞬間も特別になる。」
その言葉に、私の胸は一気に熱くなった。
この日を境に、私の世界は彼とともに輝き始めた。瞬間を切り取る彼のレンズの中で、私たちの物語は永遠に続いていくように感じた。
恋は、出会った瞬間に始まることがある。
それが運命かどうかは、あとからついてくる。